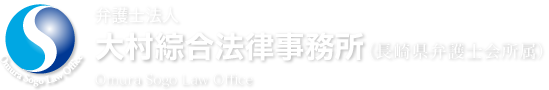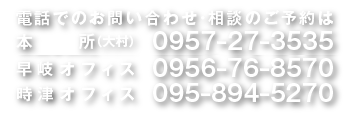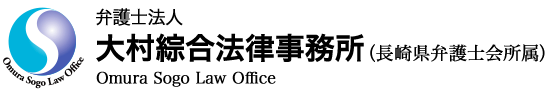Archive for the ‘相続・遺言’ Category
遺産がどれくらいあると相続税がかかりますか。
原則として、課税遺産総額が遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))以下である場合には相続税はかかりません。また、課税遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても、贈与税額控除(暦年課税贈与税)、配偶者控除、未成年者控除、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税が発生しないこともあります。
なお、相続人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、納税する必要があります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、ほぼ、改ざん・紛失・隠蔽のおそれがありません。弁護士に依頼して作成するメリットとしては、①ご依頼者様のご要望に沿った法的に不備のない遺言書を作成できること、②公正証書遺言を作成するには、公証人役場との打合せが必要であり、また、法律上、証人2名以上が必要とされていますが、この証人の準備等もすべて弁護士に任せることができます。
当事務所では、公正証書遺言作成のご依頼をお受けしておりますので、遺言書を残したいとお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
自筆遺言証書保管制度とは、どのような制度ですか。
自筆証書遺言保管制度とは、2020(令和2)年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆遺言証書を法務局に預けることができる制度のことをいいます。
これまで自筆遺言証書は、家庭裁判所の検認手続が必要でしたが、この制度を利用することにより、検認をせずに相続の手続を行うことができます。
申請手続は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局に、遺言書、顔写真付きの本人確認書類、住民票、遺言書の保管申請書等を持参して行います。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
配偶者居住権とは、どのようなものですか。
配偶者居住権とは、被相続人の相続人である配偶者が、被相続人所有(若しくは被相続人と配偶者との共有)の建物に相続開始の時に居住していた場合に、その建物全部を、原則として終身の間継続して無償で使用、収益することのできる権利をいい、2020(令和2)年4月1日以降に発生した相続につき適用されます。
なお、配偶者居住権は、残された配偶者の自宅建物での居住や被相続人死亡後の生活を保護するために新設されたものですが、その権利を取得するための要件としては、相続開始後の遺産分割によって配偶者居住権を取得させることとしたり、配偶者居住権が遺贈(遺言により無償で贈与されること)の目的とされていたりする必要があり、住み続けているだけで当然に取得できるわけではありません。
また、配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば、権利としては発生しますが、第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物が被相続人の所有ではなく、被相続人が相続人である配偶者以外の人と共有していた場合には、その建物は配偶者居住権の対象にはなりません。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
法定相続情報証明制度とは、どのような制度ですか。
不動産の所有者が(登記名義人)が死亡した場合、相続人への相続登記(所有権移転登記)が必要になりますが、その登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、空き家問題等の一因になっていることから、相続登記の促進を目的として、法務省において新設された制度です。
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において利用できるようになりました。
具体的には、相続人が登記所に対し、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の書類、及び,その戸籍謄本等の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその内容を確認した後、相続人に対し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという手続きの流れになります。
この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きのほか、被相続人名義の預貯金の払出し等、様々な相続手続きに利用できるメリットがあります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
不在者財産管理人とは、どのようなものですか。
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に、家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます(民法25条1項)。
家庭裁判所より選任された不在者財産管理人は、主に、不在者の財産の現状を維持するために必要な行為をする権限を持っていますが、遺産分割協議をしたり、不在者の不動産等の財産を処分したりする行為は、その財産管理人の権限を超えることになりますので、このような場合には、別途、家庭裁判所に「権限外行為許可」の審判の申立てをして、その許可を得る必要があります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
相続財産管理人とは、どのようなものですか。
相続人のあることが明らかでないとき[民法951条](相続人の相続放棄により、相続する者がいなくなった場合も含まれます。)に、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払う等して清算を行います。
なお、清算後に残った財産は、国庫に帰属させることになりますが[民法959条]、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
限定承認とは、どのような手続きですか。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)
② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)
③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)
相続の限定承認の申述は、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があり、相続人の一人だけが限定承認の申述をすることはできません。
また、相続の限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、限定承認をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に限定承認の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。
なお、相続の限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
相続放棄とは、どのような手続きですか。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)
② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)
③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)
相続放棄の申述は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、相続放棄をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なお、相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
公正証書遺言とは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、公証人が、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者より聞き取った遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印するものです。
公証人が遺言者の遺言であることを確認していますので、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされるといった心配もありません。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑